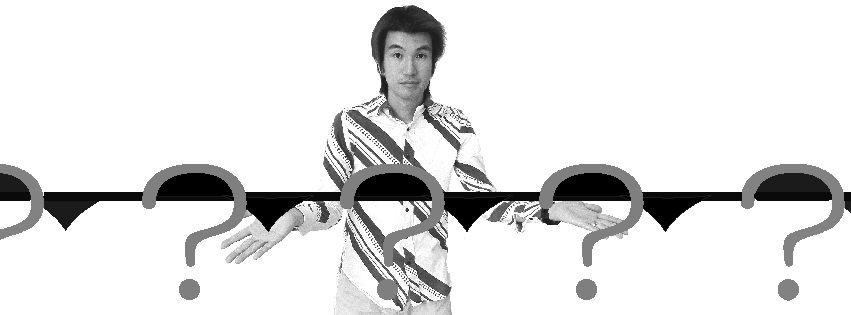梅雨の時期になると天気予報でよく聞く「梅雨前線」。
5月から7月の天気図で、東西に停滞前線の記号で描かれる前線のことです。
梅雨の長雨をもたらす「梅雨前線」は、天気図上では、とりあえず1本だけ描いてあります。
が!
実は、同時に2本できるてることがあるって知ってました?
今から20年前、モテサクは、名古屋大学の博士課程で梅雨の研究をしていました。
そのときに出した2004年の論文で、従来の梅雨前線とは別に「水蒸気前線」という新しい前線が発見した、という主張を展開しました。
あれから20回の梅雨をずっと観察して改めて見直すと、これがやっぱり改めて面白い話なので、ちょっと整理してみました。
そもそも前線って何だっけ
前線っていうのは、簡単に言うと「性質の違う空気の塊がぶつかる境界線」のことです。
普通の前線は、冷たい空気と暖かい空気がぶつかるところにできます。冬によく聞く「寒冷前線」なんかがそうですね。温度差があるところに前線ができる、これが基本的な考え方でした。

梅雨前線の不思議な特徴
ところが梅雨前線って、ちょっと変わってるんです。
温度差はそんなにないのに、なぜか前線ができて、しかも大量の雨を降らせる。
しかも、天気図で描かれる前線記号をまたいで、南北に数百kmの広い範囲に。
これ、気象学者の間でも長年「なんでだろう?」って思われてたんですね。
で、色々な人が研究して、梅雨前線は温度差は普通の前線より小さいけど、「水蒸気の量の差」は明瞭だ、という特徴がわかってきました。
湿った空気と乾いた空気の境界線、それが一般的に言われる梅雨前線の特徴です。
解像度を上げたら、もう1本見えてきた
ここからが本題です。
昔は、気象データの解像度が低かったので、梅雨前線を「太い帯」として見ていました。東西に伸びる幅広い雨雲の帯、みたいなイメージです。
でも2000年ごろのモテサクが梅雨の研究を始めた頃から、コンピュータの性能と気象モデルの性能が急激に上がって、もっと細かく天気を見ることができるようになりました。
解像度は100kmくらいで見ているたのが、5〜20kmくらいまで一気に上がってクッキリ見えるようになったんです。
そしたら、なんと、その「帯」の中に2本の「線」が見えてきたんです。
2つの前線の正体
1本目は、従来から知られていた「梅雨前線」本体。これは北側のやや冷たく乾いた空気と、南側の暖かく湿った空気の境界線です。温度差は弱いけど、ちゃんとあります。
そして2本目が、モテサクが論文の中で新しく名付けた「水蒸気前線」。
これが実は、暖かい空気同士の境界なんです。温度差はほとんどない。
じゃあ何が違うかというと、片方は大陸から来た湿った空気、もう片方は海から来た湿った空気。
同じ湿った空気でも、大陸と海では水蒸気の量がかなり違うんですね。
その境界線が「水蒸気前線」というわけです。
なんで2本あると雨が降りやすいの?
面白いのは、この2本の前線が重なったり離れたりしながら、複雑に相互作用することです。
大陸と海では地面の粗さが違うので、同じ南西風でも風速に差が出ます。その風速差で空気がぶつかって上昇気流ができる。そこに大量の水蒸気があるから、雨雲が発達しやすくなるんです。
2本の前線があることで、雨を降らせるメカニズムがより複雑になっているというわけです。
とくに、北側にある梅雨前線の本体が、南下していくときは、雨が急激に強くなりやすい。
それは、南側の水蒸気前線とぶつかったときに、一気に雨雲に供給される水蒸気の量が増えるからです。

まとめ:見方を変えると新しいものが見える
この話を思い出しながら改めて面白いと思うのは、「解像度を変えると違うものが見える」という点です。
遠くからぼんやりと1本の太い帯だと思って分析することも大事な見方です。
でも、実は近づいて解像度を上げると、2本の細い線の組み合わせだった。
数値モデルというテクノロジーの進歩で、今まで見えなかったものが見えるようになって、自然現象の理解が深まる。
これって、気象学に限らず、いろんな分野で起きていることなんじゃないでしょうか。
梅雨のジメジメした季節、天気予報で「梅雨前線」って聞いたら、「ああ、あれ実は2本あるんだよな」って思い出してもらえると嬉しいです。
自然って、知れば知るほど奥が深いですね。