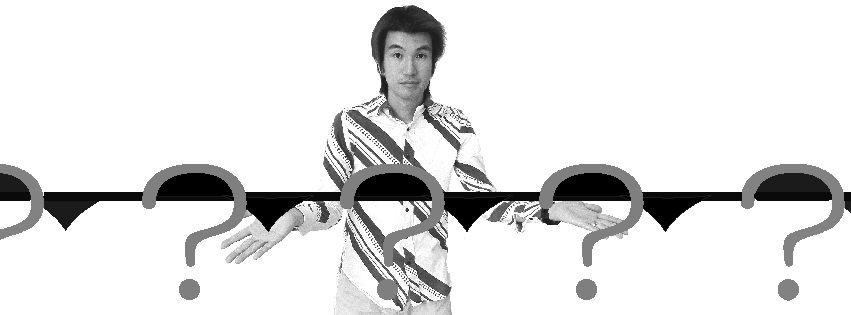は、一般向けの読み物と言うことで、英語論文は、本文中に掲載していません。
ただ、中には、原作を読むことに挑戦してみたいと思って頂ける方もおられるかもしれないので、ここに原著論文リストを掲載しておきます。
第2章「梅雨前線の姿」の原作
茂木耕作,2006:東シナ海上の梅雨前線南側における降水系の形成機構〜水蒸気前線の発見〜―2005年度山本・正野論文賞受賞記念講演―. Vol. 53, No. 8, 2006, 3-17.
茂木耕作,2009:新用語解説「水蒸気前線」. Vol. 57, No.1, 55-56.
Moteki, Q., H. Uyeda, T. Maesaka, T. Shinoda, M. Yoshizaki, and T. Kato, 2004a: Structure and development of two merged rainbands observed over the East China Sea during X-BAIU-99 part I: Meso-beta-scale structure and development processes. J. Meteor. Soc. Japan, 82, 19-44.
Moteki, Q., H. Uyeda, T. Maesaka, T. Shinoda, M. Yoshizaki, and T. Kato, 2004b: Structure and development of two merged rainbands observed over the East China Sea during X-BAIU-99 part II: Meso-alpha-scale structure and build-up processes of convergence in the Baiu frontal region. J. Meteor. Soc. Japan, 82, 45-65.]
Moteki, Q., T. Shinoda, S. Shimizu, S. Maeda, H. Minda, K. Tsuboki, and H. Uyeda, 2006: Multiple Frontal Structures in the Baiu Frontal Zone Observed by Aircraft on 27 June 2004. SOLA, 2, 132-135.
全て英語で記述された専門的な学術論文なので、若干ハードルは高いですが、本格的な研究に挑戦してみたい方は、下記の和文解説にも詳しいので併せて読んでみるのも良いかもしれません。
茂木耕作,2006:東シナ海上の梅雨前線南側における降水系の形成機構〜水蒸気前線の発見〜―2005年度山本・正野論文賞受賞記念講演―. Vol. 53, No. 8, 2006, 3-17.
茂木耕作,2009:新用語解説「水蒸気前線」. Vol. 57, No.1, 55-56.
3.1節「南風と太陽」の原作
Hiroyuki YAMADA, Biao GENG, Hiroshi UYEDA and Kazuhisa TSUBOKI, 2007: “Thermodynamic Impact of the Heated Landmass on the Nocturnal Evolution of a Cloud Cluster over a Meiyu-Baiu Front”. Journal of Meteorological Society of Japan, Vol. 85, 663-685.
Hiroyuki YAMADA, Biao GENG, Hiroshi UYEDA and Kazuhisa TSUBOKI, 2007: “Role of the Heated Landmass on the Evolution and Duration of a Heavy Rain Episode over a Meiyu-Baiu Frontal Zone”. Journal of Meteorological Society of Japan, Vol. 85, 687-709.
Hiroyuki YAMADA, Biao GENG, Krishnareddigari Krishna REDDY, Hiroshi UYEDA and Yasushi FUJIYOSHI, 2003: “Three-Dimensional Structure of a Mesoscale Convective System in a Baiu-Frontal Depression Generated in the Downstream Region of the Yangtze River”. Journal of Meteorological Society of Japan, Vol. 81, 1243-1271.
全て英語で記述された専門的な学術論文なので、若干ハードルは高いですが、本格的な研究に挑戦してみたい方は、下記の和文解説にも詳しいので併せて読んでみるのも良いかもしれません。
篠 田 太 郎,山 田 広 幸,遠 藤 智 史,田 中 広 樹,上 田 博,2009:中国華中域における大気境界層・降水システム研究の進展 ~GAME/HUBEX 特別集中観測からの10年~,天気,59,971-981.
3.2節「西風と対流」の原作
Sampe, T., and S. P. Xie, 2010: Large-Scale Dynamics of the Meiyu-Baiu Rainband: Environmental Forcing by the Westerly Jet. Journal of Climate, 23, 113-134.
全文を読むには購読の課金があります(2013年1月以降には無料購読が可能になります)が、示したURLからは英文の要旨を読むことができます。梅雨前線について気候力学的な研究に挑戦してみたい方には、一読をお薦めします。
世界最長の立ち読みPDF(78ページ/168ページ,14MB):
→ http://bit.ly/Ja3A5d
Amazonなか見検索も世界最長
→ http://amzn.to/RnVQM1
世界初!本の予告編ムービー(3分):
→ http://bit.ly/Ir2E89
本の内容を出し惜しみなく,かつフルカラーで!
一般公開講演会Youtubeビデオ(90分):
→ http://bit.ly/OuX75r
全文読めちゃいます!(未完成の初校ですけれども)
自由にコメントを入れて頂けます.
校正時に皆さんから頂いたコメントもご覧頂けます.
→ http://bit.ly/R5XPma
概要:
「科学は小説より奇なり」! !
付き合いにくい梅雨を楽しむための見方とは?
不快を愛着に、不思議を納得に、知識を理解に変える旅へご案内します。
現役の若手気象観測研究者、
通称モテサクこと、茂木耕作研究員が、
梅雨と付き合いやすくなるための三つの体験ツアーにご案内します。
当たり前に見ていた天気図の中にある意外な発見、
梅雨を観にでかけた際の予想外の興奮、
そして理解が深まるにつれて増える出会いと感動と新たな謎。
梅雨について一般的に言われていること、
ちょっと踏み込んだ話、
最先端の研究の現状を「体感」するための一冊。
みなさんも経験的に
「聞いたことは、忘れがち。
観れば、覚えていられる。
でも本当に理解できるのは,取り組んだとき。」
ということを感じていませんか。
梅雨前線について何を取り組めば、
理解できるのか?
あなたもまずはその扉を開いて出かけてみましょう!